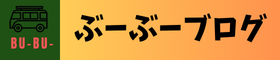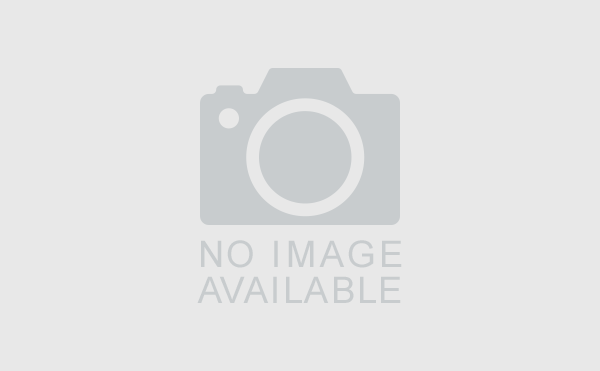【2025年最新版】ハイエースの床張りは車検に通る?通らないパターンも徹底解説!

こんにちは、元整備士のブーブーです。
最近はハイエースを自分好みにカスタムして、車中泊やアウトドアを楽しむ人が本当に増えましたね。
その中でも人気のカスタムが「床張り」ではないでしょうか?
見た目もスッキリして、荷物が載せやすく、まるでキャンピングカーのような仕上がりになります。
でも、「床張りしたら車検に通らないのでは?」という不安を抱く人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、ルールを守って施工すればハイエースの床張りは車検に通ります。
ただし、「知らずにやると車検NG」というポイントがあるのも事実です。
この記事では、床張りの注意点から車検に通すためのコツまで、やさしく分かりやすく解説します。
Contents
ハイエースに床張りする3つのメリット
まずは、床張りの「良さ」を改めて整理しておきましょう。
実際に僕自身もハイエースを床張りして使っていますが、その快適さは一度味わうと戻れません。
① 荷物の積み下ろしが断然ラクになる
ハイエース純正の荷室は金属の凹凸が多く、荷物が安定しにくいんですよね。
床張りをすることでフラットな面ができ、重い荷物もスムーズにスライドできるようになります。
DIYや仕事で工具や資材を積む人にもおすすめです。
またベッドキットなどやテーブルなど今後、作る場合にも床面が平らになっていないと後々、大変になります。
② 掃除が圧倒的にラク
床張りをしていると、泥や砂が溜まりにくく、掃除がかなり簡単になります。
特に合板やクッションフロアを敷くと、濡れたタオルでサッと拭くだけでOKなんですよ。
「釣り」「サーフィン」「キャンプ」など、アウトドア派には特にうれしいメリットですね。
③ 車中泊や仮眠スペースが快適に
フラットな床は、寝るときの快適さに直結します。
マットを敷けばベッドとしても使えるし、簡易的なテーブルや収納を置いても安定します。
長距離ドライブの休憩にも便利です。
【2】ハイエースの床張り、車検に通すためのポイント
ここからが本題です。
床張りをしても「車検に通る場合」と「通らない場合」があります。
この違いを知らずにDIYしてしまうと、せっかくの愛車が車検でストップしてしまうことも…。
① セカンドシートの固定方法に注意
まず大切なのがセカンドシートの固定方法です。
車検では、セカンドシートはボディ(床の鉄板)に直接固定されている必要があります。
そのため、床張りした合板の上からセカンドシートを置いてボルトで固定するのはNGです。

理由は人を乗せる大事なシートがしっかりとボルトで固定されていないと危ないからだよ!
合板を施工する際には、セカンドシートの取り付け位置を避けて板を加工し、純正の固定ポイントを使えるようにしておきましょう。
これは意外と見落としがちな部分で、車検時に「シートの固定が不十分」と判断されるケースが非常に多いです。
② 取り外し可能な構造にする
車検に通すうえで最も手軽で確実なのが、「取り外せる床張り」にすること。
つまり、合板をボディに固定せず「荷物」として扱える状態です。
ベースの鉄板にネジ止めせず、床面にピッタリ収まるようにカットして敷くだけでも十分機能します。
ただし車検の検査の時には空車状態が必須になるので合板は降ろして車検を受けなくてはいけません。
▼ノブボルトによる“簡易固定”は合法的な抜け道
ノブボルトとはこんなやつです↓
実はここが大きなポイントです。
床張りを完全に固定してしまうと重さにより「構造変更」が必要になるケースが出てきますが、
ノブボルト(手で締め外しできるボルト)を使って合板を固定しておくと、
「工具を使わずに取り外しできる=簡易的取り付け」とみなされ、車検時に板を外す必要がなくなる場合があります。
ハイエースの後ろ側にはタイダウンフックと言う荷物を固定する為のフックがついていますが合板で床張りする場合このフックは邪魔になるので取り外します。
このボルト穴にノブボルトを取り付けするのがお勧めです。
つまり、この方法は“合法的な抜け穴”ともいえるテクニック。
他のサイトではあまり紹介されていませんが、ちゃんと法律を守った正規の方法です。
見た目もスッキリして、車検対応と実用性を両立できる筆者もやっているおすすめの方法です。
③ 固定式にするなら「構造等変更申請」が必要
もしビス止めや接着剤でしっかり固定したい場合は、構造等変更申請が必要になります。
この手続きは「車の構造を変更した」という届け出のようなもので、陸運局で実車検査+書類審査を受けることになります。
合格すると、車検証に「改」と記載され、正式に公道を走行できます。
ただし、DIYレベルだと不合格になることもあるため、専門業者に相談するのがおすすめです。
④ 素材・重量にも注意
車内で使う素材は「難燃性素材」であることが定められています。
木材や合板を使う場合でも、JABIA(日本自動車車体工業会)認定の難燃証明があるものを選びましょう。
また、床材が重すぎると車両重量が増え、車検NGになることもあります。
ノブボルトで固定であれば問題ありませんが燃費の悪化にもつながるのであまり重量は重くならないようにしましょう。
軽量合板やアルミパネルを使うのがおすすめです。
ちなみに3ミリ以上の木材は難燃性と認められています。
【3】DIY床張りで注意したい3つの落とし穴
せっかくカスタムしたのに「車検に落ちた…」という人の多くが、この3つを見落としています。
① 座席を外したままにしている
後部座席を外してそのまま床張りしてしまうと、乗車定員が変わるため車検NGです。
どうしても外したい場合は、構造変更+4ナンバー化が必要になります。
② 保険会社への申告を忘れる
構造変更をした場合は、車検証の内容が変わるため保険会社にも届け出ましょう。
届け出を忘れると、万が一の事故で保険金が下りないこともあります。
③ ディーラー車検では断られるケースも
純正以外のカスタムをした車は、ディーラーでは車検を断られることがあります。
そういった場合は、ユーザー車検やカスタム車専門の整備工場を利用しましょう。
自分で車検を通すのも意外と簡単で、費用も安く済みます。
【4】キャンピング仕様にしたい人向けアドバイス
もし本格的に「車中泊仕様」にしたいなら、いっそ8ナンバーのキャンピングカー登録を考えるのもアリです。
以下の条件を満たせば、正式にキャンピングカーとして登録できます。
- ベッドの長さ:180cm以上
- 幅:50cm以上
- 耐久性があり、大人が寝ても問題ない構造
- 炊事設備(水タンク10L以上、排水タンク付き)
- 換気が確保されている
8ナンバー化すると車検費用がやや高くなりますが、改造の自由度はぐっと上がります。
趣味で車中泊を楽しむ人にはおすすめです。
注意! R4年以降はキャンピングカーの法律の要件が一部変更になっています。
【5】まとめ|安全に・合法的にカスタムしてハイエースをもっと楽しもう
ハイエースの床張りは、
- 荷物が積みやすい
- 掃除が簡単
- 寝床にもなる
といったメリットがあり、使い勝手を大きく変えてくれます。
ただし、セカンドシートの固定位置や素材、重量、そして取り付け方法を間違えると車検に通らなくなることもあります。
ノブボルトによる簡易固定は、合法的に施工できる“隠れたテクニック”です。
DIYで施工する場合は、この方法を取り入れながら安全かつスマートに仕上げましょう。
床張りを正しく施工して、あなたのハイエースライフをより快適に、そして安心に楽しんでくださいね。
良かったらこちらの記事もあわせて読んでみてください。